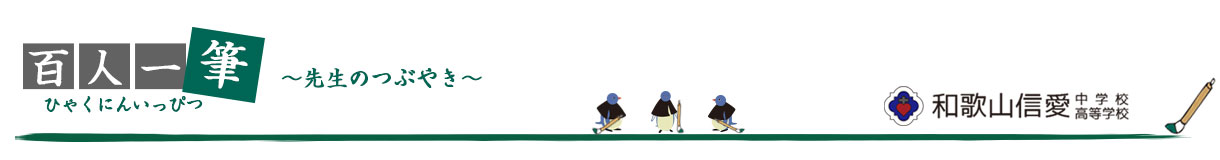すっかり秋めいて気温が下がってきましたね。つい先日まで暑くてたまらなかった気がするので暖房器具などの準備が追いついておりません。生徒の皆さんも関係者の方々も、寒暖差に気をつけてお過ごしください。
今回は暑くてたまらない盛りに行ってきた場所の話をしようと思います。と言っても、和歌山県に比べるとかなり涼しい場所でした。
行ってきたのは青森県です。まず和歌山から東京に向かい、東京見物をして一泊し、翌日朝の東北新幹線に乗って新青森駅に向かいました。(時間もお金もかかるのですが、どうしても飛行機が怖くて……)その日のうちは青森駅周辺を散策したのち、移動して五所川原で一泊。翌日に向かったのが青森の目的地「斜陽館」です。
斜陽館とは、作家・太宰治の生まれ育った家をそのまま保存し、太宰治に関する資料を展示する文学館です。
五所川原駅からタクシーに乗り、見渡す限りの田んぼを車窓から見ているとほどなく到着。
まずはそのあまりの大きさに驚きました。太宰治本人が「この父は、ひどく大きい家を建てた。風情も何も無い、ただ大きいのである。」と著作「苦悩の年鑑」に書いてある通り、明治時代に建てられた個人の住む家とは思えないほどの大きさです。大きいだけでなく、一階は和風の間取りで和室、二階は洋風の間取りで洋室を配置していたり、遠くからも見えるような赤い屋根が印象的だったりと、とにかく豪壮でお金のかかったつくりになってもいるところが特徴です。展示内容も充実しており、実家ならではのエピソードもたくさん知ることができました。
(外から見ると和風なのですが、内部にはこんなに洋風なお部屋も。)
斜陽館で展示を見た後、「太宰治疎開の家」にもお邪魔しました。ここはその名の通り太宰治が太平洋戦争末期に実家に疎開した際に妻子と一緒に滞在した離れを移築した施設で、実際にその疎開体験をつづった作品に出てくる場所でもあります。ここでは親切なガイドの方にたくさんお話を聞くことができました。太宰治(本名:津島修治)の実家・津島家は、当時の青森県では誰もが知る大地主。先ほどタクシーで見ていた辺りの田んぼは、当時はほとんどすべて津島家のもので、そこから一定量(半分くらい?)が自動的に津島家に入ってきていたそうです。加えて、実際にお米を作っている小作人たちから襲われる危険も考慮し(「小作争議」と聞くと日本史の授業などで聞いたことがある人も多いのでは)、新しく建てた津島家の邸宅(これが斜陽館にあたるそうです)の近くまで警察署を移動させ、近隣の町の役場などの行政機構もその近隣に移ってきたとか。ちょっと現代の感覚では測れないレベルのお金持ちエピソードの数々を聞き、圧倒されておりました。
太宰治が(現代の言葉で言うところの)「実家が太い」人間であったことは、彼の著作の多くに影響しています。そんな実家に生まれながら、数々の良くない行いにより絶縁された経験もありまして、先述の疎開時も複雑な思いを抱えての帰郷だったことが作品から読み取れます。特に「帰郷」の中に、太宰治と一緒に初めて青森を訪れる妻が故郷を気色がきれいで明るい土地だとほめた際の「『そうかね。』」「『僕には、そうも見えないが。』」と反応する部分が出てくるのですが、現代でも地元をほめられてなぜか素直に喜べず「何もないとこだよ~」などとけなしてしまうの、あるあるだな~……と思いながら読みました。これ以外にも、太宰治の作品には現代人にも深く共感できる内容が多いと思います。「読書の秋」でもあることですし、秋の夜長に太宰治の作品に触れてみるのはいかがでしょうか。